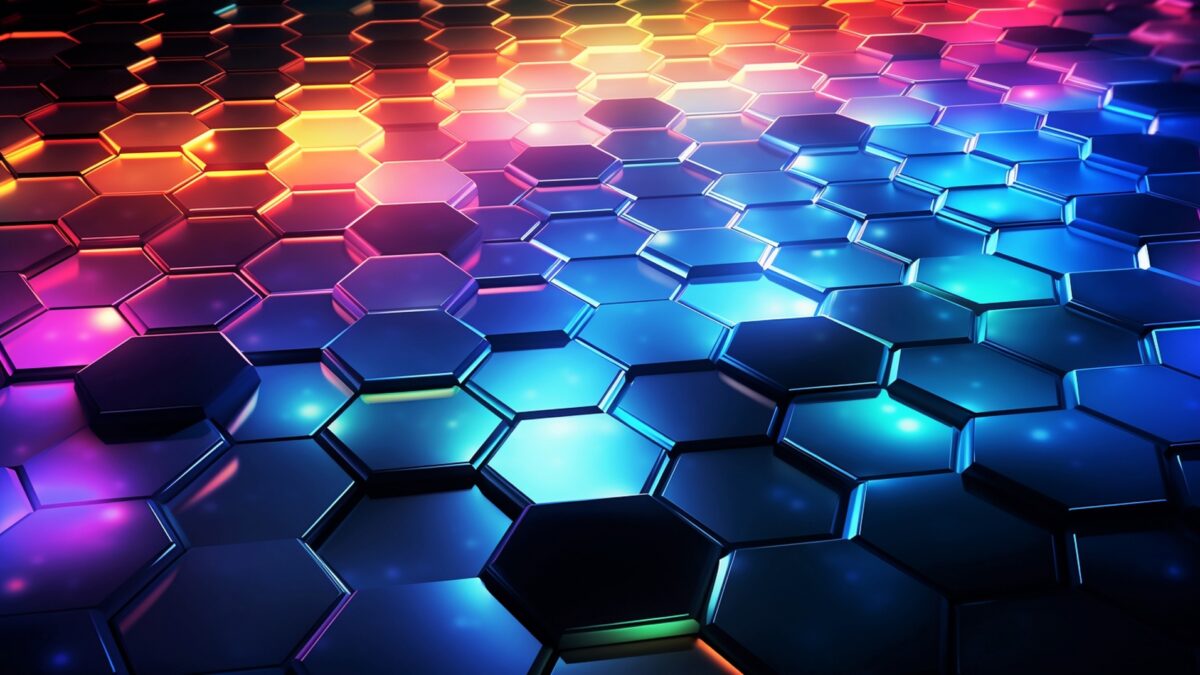インテルの次世代モバイル向けSoC「Panther Lake」について、2025年第4四半期まで生産が遅れるとの報道があったが、同社はこれを完全に否定した。Morgan Stanleyカンファレンスに登壇したジョン・ピッツァー氏は、Panther Lakeは予定通り2024年下半期にローンチされ、18Aプロセスの進捗も問題ないと発言。さらに、Meteor Lakeと比較して歩留まりが向上していることも明かされた。
また、インテルは18AプロセスがTSMCのN2プロセスと競争可能な水準にあることを強調し、2024年下半期には顧客向けサンプルの提供を開始する予定である。Panther Lakeの正式ローンチ後、本格的な大量生産は2026年に開始される見込みであり、インテルのファウンドリー事業にとって重要なマイルストーンとなる。
インテルの次世代18Aプロセスは順調に進行 Panther Lakeの歩留まりも向上

インテルは、次世代の高性能プロセス「18A」を用いたSoC「Panther Lake」が計画通り進行していることを明言した。近年、同社は半導体製造技術の進化に注力しており、18Aプロセスはその重要なステップと位置づけられている。
特に18Aプロセスでは、従来のFinFET構造からRibbonFETと呼ばれる新しいトランジスタ設計を採用し、電力効率と性能向上を両立させる狙いがある。Morgan Stanleyカンファレンスに登壇したジョン・ピッツァー氏は、Panther Lakeの歩留まりがMeteor Lakeと比較して改善されていると発言しており、技術面での進展が見られる。
さらに、18Aプロセスの成功は、インテルが再びファウンドリー市場での競争力を強化するカギとなる。近年、TSMCやサムスンが最先端プロセスをリードしてきたが、インテルは18Aを通じてその差を縮めようとしている。特にSRAM密度の向上は、今後のチップ設計において大きなアドバンテージとなる可能性がある。
Panther Lakeの本格量産は2026年 インテルの製品戦略と市場への影響
インテルは、Panther Lakeの正式なローンチを2024年下半期に予定しているが、本格的な量産は2026年になると明言している。このスケジュールは、過去のMeteor LakeやLunar Lakeの展開と類似しており、まず少量生産を開始し、その後、需要に応じて生産規模を拡大する流れとなる。
2026年の大量生産開始により、Panther Lake搭載のノートPCやハイエンドモバイルデバイスが市場に登場する可能性が高い。18Aプロセスの採用により、消費電力を抑えつつ、パフォーマンスの向上が期待されるため、特にゲーミングやクリエイティブ用途のユーザーにとっては注目すべき製品となるだろう。
一方で、量産開始までの期間、インテルは既存のMeteor LakeやLunar Lakeを市場に投入しながら、次世代製品の準備を進めることになる。このスケジュール感は、他社の競争状況にも影響を与える可能性があり、特にTSMCのN2プロセス採用チップとの比較が重要なポイントとなる。インテルが18Aプロセスでの競争力を示せるかが、今後の市場シェア争いを左右することになる。
インテルの18AプロセスとTSMC N2プロセスの競争 どちらが市場をリードするか
インテルの18AプロセスとTSMCのN2プロセスは、次世代半導体技術の競争において重要な比較対象となる。TSMCのN2プロセスは2025年に量産開始予定であり、先行する形で市場に登場する。一方、インテルの18Aは2024年下半期からサンプル出荷を開始し、2026年に本格量産へと移行するため、製造タイミングには若干のズレがある。
18Aプロセスの強みは、RibbonFETやPowerViaといった新技術の導入による高密度設計と電力効率の向上にある。特にPowerViaは、従来のチップ設計とは異なる電源供給アーキテクチャを採用し、配線遅延を最小限に抑えることができる。この技術が成功すれば、従来のFinFETベースのプロセスと比べて大幅な性能向上が見込まれる。
一方、TSMCのN2プロセスは、現行のN3プロセスを改良しつつ、トランジスタ密度と消費電力のバランスを最適化することを目指している。すでにAppleやAMDなどの顧客を抱えているTSMCは、市場投入の早さを武器にしており、18Aとの競争は熾烈なものとなる。インテルがファウンドリー事業の再興を狙う中で、どちらのプロセスが市場により大きな影響を与えるかが今後の焦点となる。
Source:Wccftech