Microsoftは、これまで公式サポートページで提供していた、TPM 2.0非搭載のPCにWindows 11をインストールするためのレジストリ編集による回避策の記載を削除した。この変更は、2024年12月中旬に行われたと見られ、現在では物理メディアを使用してのインストール方法のみが記載されている。
これにより、非対応PCでのWindows 11導入が一層困難になる可能性がある。ユーザーは、今後のアップデートやサポート状況に注意を払う必要があるだろう。
Microsoftが削除した回避策の内容とは
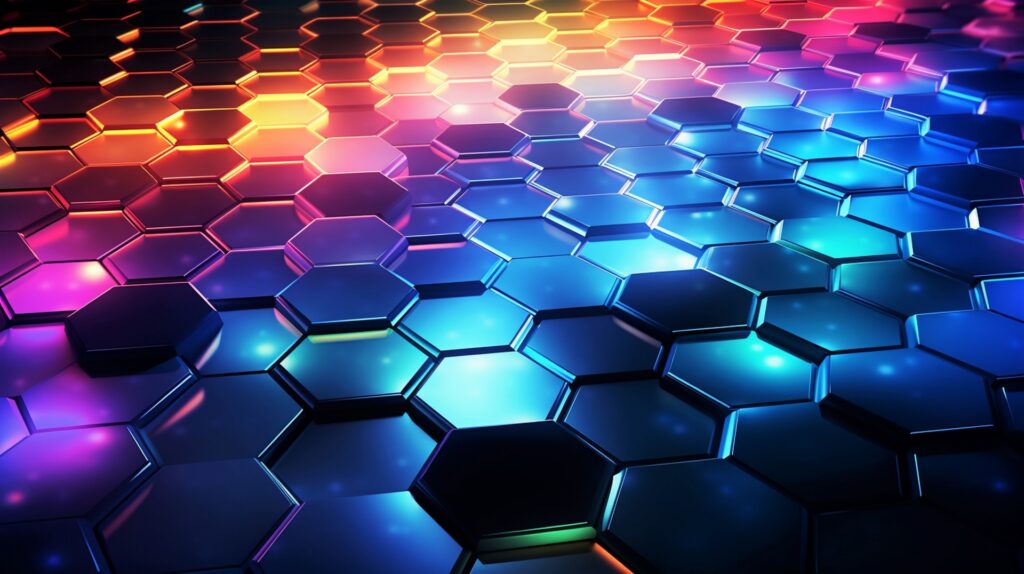
Microsoftは、Windows 11のハードウェア要件を満たしていないPCでもOSをインストールできる方法を公式に案内していた。この方法は、Windowsのレジストリを編集し、TPM 1.2を搭載したPCでWindows 11のインストールを可能にするものだった。
しかし、2024年12月にMicrosoftの公式サポートページからこの記載が削除されたことが確認されている。Neowinの報告によれば、Wayback Machineの履歴を調査した結果、12月12日から14日の間にページが更新され、回避策の記載が削除されたという。
この変更によって、TPM 2.0を搭載していないPCでのWindows 11導入はより難しくなった。ただし、USBメモリやDVDといった物理メディアを使用したインストール方法の説明は依然として残されている。
つまり、TPM 1.2環境であればインストールできる可能性はあるが、公式に認められた回避策ではなくなった点が重要だ。Microsoftは、回避策削除の理由について明確な説明を行っておらず、これが今後のアップデートでさらなる制限につながるのかどうかは不透明である。
また、Windows Server 2025のインストールチェックを利用する別の回避策も過去には存在していたが、Microsoftは2024年8月にこれを封じる対策を講じた。この動きからも、同社がWindows 11のハードウェア要件を厳格に適用しようとしている姿勢がうかがえる。
回避策封じの背景にあるMicrosoftの意図とは
MicrosoftがWindows 11のハードウェア要件を厳格化する背景には、セキュリティ強化の方針があると考えられる。TPM 2.0は、PCの安全性を向上させるためのセキュリティチップであり、Windows 11の設計上不可欠な要素とされている。
特に、BitLockerによるデータ暗号化やWindows Helloの生体認証機能など、TPM 2.0の活用が前提となる機能が増えている。Microsoftは「Windows 11をより安全なOSにする」という方針を掲げており、TPM 2.0の要件を維持することでセキュリティリスクの低減を図っているとみられる。
しかし、この厳格化がすべてのユーザーにとって歓迎されるわけではない。特に、比較的新しいPCであってもTPM 2.0を搭載していない機種は少なくなく、これらのデバイスがWindows 11に正式対応しないというのは不満の声が上がる要因となっている。
また、ハードウェアの買い替えを促す目的があるのではないかという指摘もあり、Microsoftが旧世代のPCを徐々に市場から淘汰しようとしている可能性も考えられる。
一方で、回避策が完全に無効化されたわけではない点も重要だ。現時点では、Windows 11のISOファイルを利用し、手動でクリーンインストールする方法が依然として機能する。
また、サードパーティのツールを活用すればTPM 2.0非搭載のPCでもインストールが可能な場合がある。ただし、Microsoftはこうしたツールに対しても対策を講じる可能性があり、今後のWindows Updateによって制限が強化されることも考えられるだろう。
サードパーティ製ツールへの影響と今後の展開
Microsoftが公式の回避策を削除したことで、Flyby11のようなサードパーティ製のツールを使用するユーザーが増える可能性がある。しかし、Microsoft Defenderは最近のアップデートでFlyby11を「Win32/Patcher」として検出し、潜在的に望ましくないアプリ(PUA)として扱っている。
これは意図的な措置なのか、それとも誤検出なのかは現時点では不明だ。Flyby11の開発者は、Microsoftに対してこの措置の理由を確認中だが、公式な回答は得られていないという。
この状況は、過去にサードパーティ製のカスタマイズツールが次々と機能しなくなった経緯と似ている。Windowsの歴史を振り返ると、Microsoftは常に「公式な方法」を維持しながら、非公式な改変や回避策を徐々に制限する方向へ進んできた。特に、Windows 10以降は強制的なアップデートの実施やサードパーティ製ツールの制限が増えており、Windows 11ではその傾向がさらに顕著になっている。
この流れを踏まえると、Flyby11のようなツールも今後のWindows Updateで動作しなくなる可能性がある。Microsoftは「セキュリティ上の理由」として非公式なインストール方法を排除し、TPM 2.0を搭載したPCのみをサポートする方向へ進むだろう。仮に現在の回避策が機能していたとしても、将来的にOSのアップデートで使用不能になるリスクは避けられない。
今後、Windows 11を使用したいユーザーにとっては、新しいハードウェアへの移行を検討する必要があるかもしれない。Microsoftが回避策の削除を進めていることを考えると、現行の回避策がいつまで有効であるかは保証されておらず、Windows 11の公式要件を満たさないPCの扱いは今後さらに厳しくなる可能性がある。
Source:The Register
