マイクロソフトは、2025年10月14日に予定されているWindows 10の公式サポート終了後も、セキュリティ更新を希望するユーザー向けに「拡張セキュリティ更新プログラム(ESU)」を提供する計画を明らかにした。個人ユーザーは年間30ドル(約4500円)で1年間のESUを購入でき、企業向けには初年度61ドル、2年目122ドル、3年目244ドルと段階的に料金が上昇するプランが用意されている。
ESUは重要なセキュリティパッチのみを提供し、新機能の追加やバグ修正、技術サポートは含まれない。マイクロソフトは、より高度なセキュリティとパフォーマンスを求めるユーザーに対して、Windows 11への移行を推奨している。ただし、Windows 11のシステム要件は厳しく、多くの既存デバイスが対応していない可能性があるため、ユーザーは自身のデバイスの互換性を確認する必要がある。
ESUの提供は、Windows 10ユーザーにとってセキュリティを維持する一つの選択肢となるが、長期的な視点ではWindows 11への移行が推奨される。
Windows 10のESU料金体系と対象デバイスの詳細
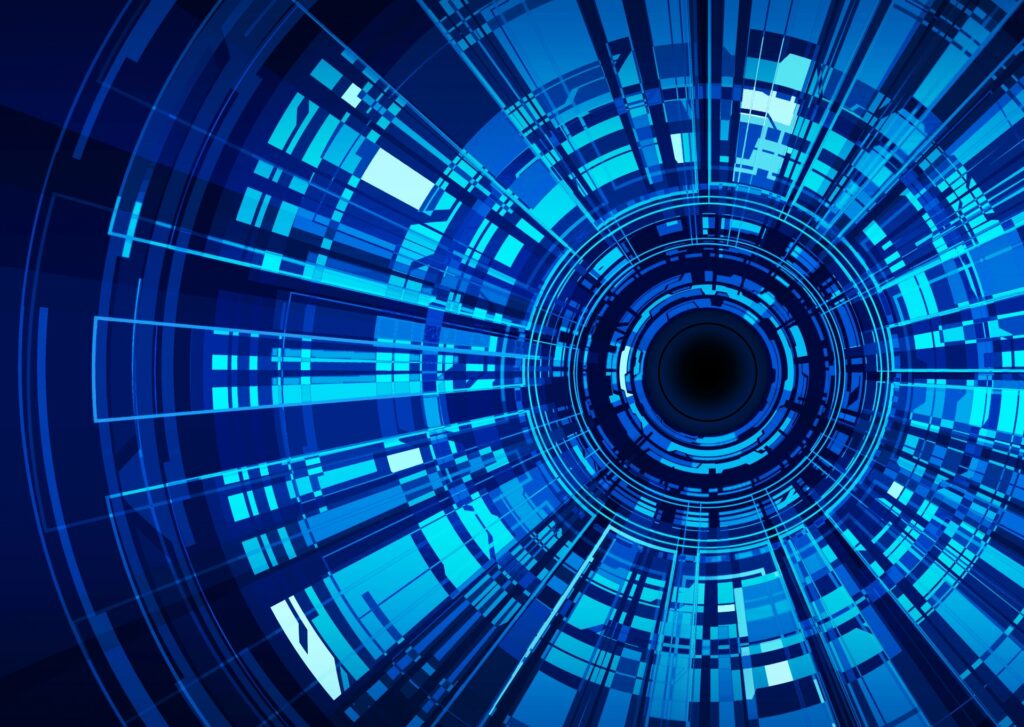
マイクロソフトが発表した「拡張セキュリティ更新プログラム(ESU)」は、Windows 10の公式サポート終了後もセキュリティ更新を受け続けるための有料オプションとなる。このプログラムでは、個人ユーザー向けと企業向けの料金体系が分かれており、特に企業向けでは年ごとに倍増する価格設定が特徴的だ。
個人ユーザーは1年間のセキュリティ更新を30ドル(約4500円)で利用できる一方、企業は最初の1年目が61ドル(約9200円)、2年目が122ドル(約1万8400円)、3年目が244ドル(約3万6800円)と段階的に増額する。これは、長期間Windows 10を使い続けることによるコスト負担の増加を意識した仕組みと考えられる。
また、ESUが適用されるデバイスには制限がある。Windows 365やAzure Virtual Desktopのクラウド環境上で稼働するWindows 10デバイスは、追加料金なしでESUを受けられるが、一般の物理PCでは有償となる。これは、マイクロソフトがクラウドサービスの利用を促進し、将来的により多くのユーザーをクラウドベースの環境へ移行させようとしていることを示唆している。
さらに、ESUはセキュリティ更新のみに限定されており、新機能の追加やバグ修正、技術サポートは一切含まれない。そのため、特に個人ユーザーは、Windows 10の使用を継続するか、Windows 11への移行を検討するかの選択を迫られることになるだろう。
Windows 11移行のハードルとTPM 2.0の問題点
マイクロソフトは、Windows 10ユーザーに対してWindows 11への移行を推奨している。しかし、その移行にはいくつかの大きな障壁が存在する。そのひとつが、Windows 11のシステム要件である「Trusted Platform Module(TPM)2.0」の存在だ。
TPM 2.0は、暗号鍵を安全に保管し、セキュアブートやBitLockerといったセキュリティ機能を強化するために設計されたハードウェアモジュールである。
しかし、すべてのWindows 10搭載デバイスがこの要件を満たしているわけではなく、特に古いPCではTPM 2.0非搭載のケースも少なくない。そのため、Windows 11へのアップグレードを希望しても、ハードウェアが対応していないために実行できないユーザーも多く存在する。
この問題により、Windows 10からの移行を阻まれるケースが増加し、ESUを利用せざるを得ないユーザーが一定数発生すると考えられる。マイクロソフトとしては、新しいPCへの買い替えを推奨する方針だが、すでに問題なく動作しているPCを手放すことに抵抗を感じるユーザーも多いだろう。また、企業にとっては、大量のPCを買い替えるコストが新たな負担となる。
こうした状況を踏まえると、Windows 10のESUを利用しつつ、Windows 11のハードウェア要件を緩和する可能性があるかどうかも注目されるポイントだ。マイクロソフトはこれまでのOS移行においてもユーザーの反応を見ながら方針を調整してきたため、今後の動向次第では一定の対応が行われる可能性もある。
Windows 10の終焉と長期的な影響
Windows 10の公式サポート終了が迫る中、今回のESU発表はWindows 10の終焉を明確にするものとなった。多くのユーザーにとって、セキュリティ更新を継続するために有償のESUを利用するか、それとも新しいPCへ移行するかという判断が求められる時期が近づいている。
また、マイクロソフトはWindows 10向けのMicrosoft 365のサポート終了も発表しており、これによりセキュリティ面だけでなく、生産性ソフトウェアの使用にも影響が出る可能性がある。特に企業では、Officeアプリケーションを中心とした業務環境を考慮する必要があり、Windows 11への移行を急ぐ企業も増えるだろう。
一方で、過去のWindows 7のサポート終了時と同様に、一定数のユーザーがWindows 10を使い続けることは予想される。特に、オフライン環境や特定の業務アプリケーションがWindows 10でしか動作しないケースでは、サポート終了後も利用を継続せざるを得ない状況が発生する可能性がある。
このように、Windows 10の終焉は単なるOSの移行問題にとどまらず、セキュリティリスクの管理、ハードウェアの買い替え、業務アプリケーションの対応といった複数の要素が絡む問題となっている。今後のマイクロソフトの方針や、新たな移行プランの登場によって、状況が変化する可能性もあるため、引き続き注視する必要があるだろう。
Source:WinBuzzer
