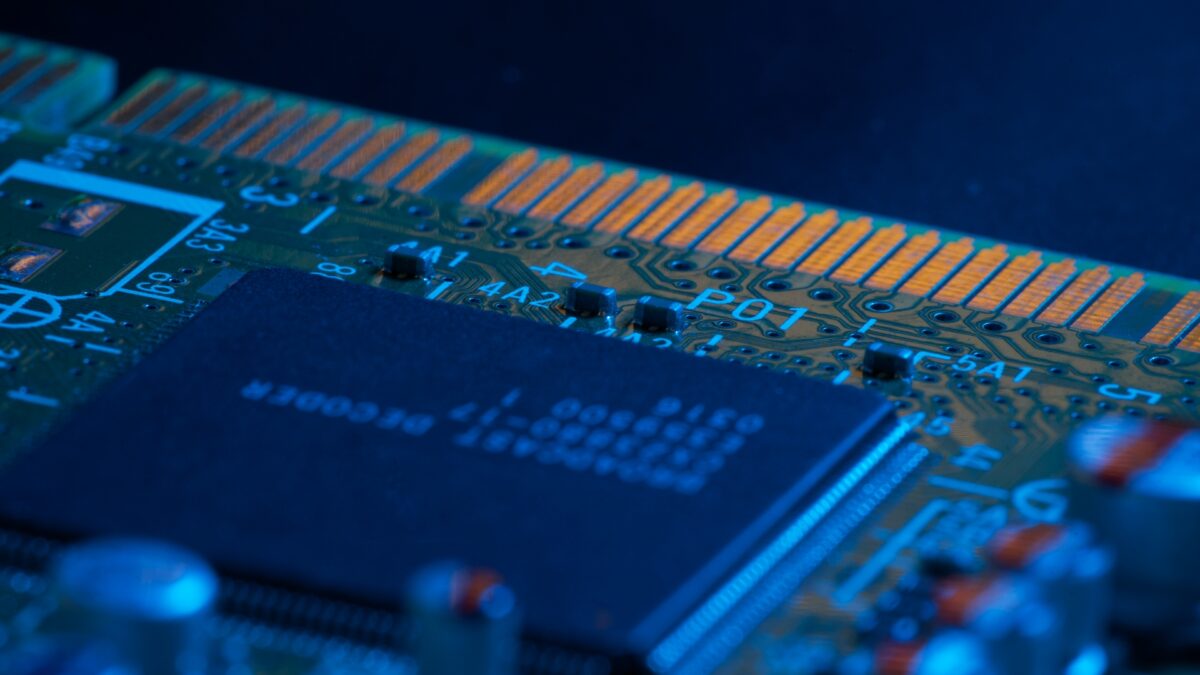Nvidiaの次世代フラッグシップGPU「GB202」のダイ構造が公開され、RTX 5090を支えるBlackwellアーキテクチャの詳細が明らかになった。ダイ中央に配置された32MBのL2キャッシュ、96個のTPC、12のラスタエンジン、GDDR7メモリとの接続を担うメモリコントローラーなど、革新的な設計が注目される。
また、GB202のダイサイズは761.56mm²と前世代AD102より24%拡大し、Nvidiaが性能向上を追求するための物理的工夫が見て取れる。新たなTSMC N4Pプロセスを採用したBlackwellアーキテクチャの設計哲学が示す未来像に期待が高まる。
GB202が示すNvidiaの技術進化と設計戦略

NvidiaのGB202は、RTX 5090を支える基盤として、Blackwellアーキテクチャの中核を成す設計となっている。中心部には32MBのL2キャッシュが配置され、2MB単位で分割されることで効率的なメモリ管理を実現している。
これを囲むように設置された96個のTPC(テクスチャ処理クラスター)は、各TPCが最大4つのSM(ストリーミングマルチプロセッサ)を備え、演算能力と画像処理性能を強化する仕組みである。このような構造は、より高いグラフィックス性能を実現するためのものと考えられる。
また、GB202ではPCIe 5.0インターフェイスやGDDR7メモリへの対応が確認されており、データ転送速度と帯域幅の大幅な向上が期待される。この進化は、リアルタイムレイトレーシングやAI活用のさらなる可能性を引き出す設計思想の表れである。
特にTSMCのN4Pノードの採用により、エネルギー効率の向上とダイサイズの最適化が可能となった。一方で、より小型なプロセスノードを採用しなかった理由として、量産性やコスト面の影響が推測される。こうした決定は、単なる性能競争にとどまらない包括的な設計戦略を反映していると言える。
GB202のダイサイズ拡大が意味する性能と課題
GB202はAD102よりも24%大きいダイサイズを持つ。具体的には761.56mm²と大幅に拡大されており、このサイズ増加はNvidiaが性能面での限界を打破しようとする姿勢を象徴している。しかし、このような巨大なダイ設計には課題も存在する。ダイサイズが大きくなるほど、製造時の歩留まり率(良品率)が低下し、コストが上昇する可能性がある。また、発熱や電力消費の増加も避けられない。
一方、GB202は過去のNvidia製品であるGH100やGV100(いずれも814mm²以上)の経験を活用している可能性が高い。これらの設計経験が、Blackwellアーキテクチャの課題を克服する上で役立っていると考えられる。
さらに、ダイサイズ拡大の背景には、CUDAコア数やL2キャッシュ量の増加による並列処理能力の強化がある。これにより、高解像度グラフィックスや複雑なAIワークロードに対するパフォーマンスの向上が期待できる。最先端技術の採用がもたらす恩恵とともに、巨大なダイ設計が市場に与える影響にも注目すべきである。
TSMC N4Pノード採用がもたらす効果と選択の意図
GB202はTSMCのN4Pノードを採用しており、これがBlackwellアーキテクチャにとって重要な要素となっている。N4Pは、前世代のN4に比べて電力効率やパフォーマンスが向上しており、高性能を実現しつつも発熱と消費電力を抑える利点がある。これにより、RTX 5090の長時間使用時における安定性が確保されると見られる。
しかし、Nvidiaが最新プロセスノードであるTSMCの3Nを採用しなかった点には議論の余地がある。3Nの採用でチップサイズをさらに縮小できた可能性が指摘されているものの、製造コストや市場投入時期を考慮した結果、N4Pが選択された可能性が高い。この選択は、Nvidiaが単なる技術競争ではなく、コスト効率や市場需要を考慮した包括的なアプローチを取っていることを示している。
このような選択は、性能と製造効率のバランスを追求するNvidiaの戦略の一端を示している。消費者にとっては、安定した供給と競争力ある価格が期待される一方で、Nvidiaが次世代プロセスへの移行をどのタイミングで進めるかが今後の焦点となるだろう。
Source:Tom’s Hardware