マイクロソフト共同創業者のビル・ゲイツは、ダラス・マーベリックスのマーク・キューバンとの対談で、スティーブ・バルマーが最新のWindows 11を旧版のWindows 10に戻すとしたらどうするかと問われ、「メディアから隠れるかもしれない」と冗談交じりに答えた。
この発言は、マイクロソフトの歴史と、同社が世界中で数十億人のユーザーを持つソフトウェア開発企業として急成長してきた背景を考えると興味深い。現在、Windows 10のサポート終了が2025年10月14日に予定されているが、依然として市場シェアの60.33%を占めており、Windows 11の36.65%を上回っている。
マイクロソフトはユーザーにWindows 11へのアップグレードを促しているが、多くのユーザーはWindows 10を使い続けている。
Windows 10の根強い人気とアップグレードの壁
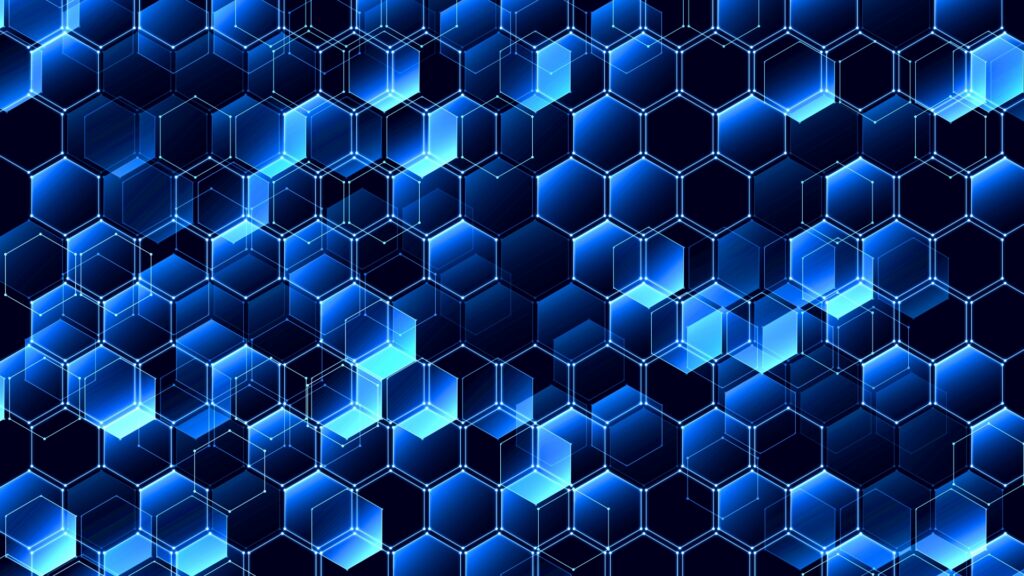
Windows 11がリリースされてからすでに数年が経過したが、Windows 10の市場シェアは依然として高く、多くのユーザーが最新OSへの移行をためらっている。2025年10月14日にWindows 10の公式サポートが終了する予定にもかかわらず、全Windowsユーザーの約60.33%が今なおWindows 10を利用しているというデータが示されている。これに対し、Windows 11のシェアは36.65%と伸び悩んでいる。
Windows 11へのアップグレードが進まない最大の要因の一つは、システム要件の厳しさだ。特にTPM 2.0(Trusted Platform Module 2.0)や特定のプロセッサ要件がネックとなり、多くの旧型PCではWindows 11をインストールすることすらできない状況にある。
加えて、新しいデザインやユーザーインターフェースの変更に対して抵抗感を示すユーザーも多く、馴染みのあるWindows 10の環境から離れたくないと考えている人が少なくない。
さらに、Windows 10が「十分に完成されたOS」と見なされている点も重要だ。過去のバージョンと比較して安定性が高く、多くのアプリケーションや企業向けシステムとの互換性も確保されている。
Windows 11の新機能は魅力的だが、アップグレードの必要性を感じないユーザーにとっては、今の環境を維持することが最も合理的な選択肢となっている。結果として、多くのPCユーザーはWindows 10のサポート終了まで可能な限り使い続ける意向を示している。
Windows 10のサポート終了がもたらす影響と選択肢
Windows 10のサポート終了が迫る中、ユーザーに求められる選択肢は大きく分けて3つある。まず、マイクロソフトの提供するExtended Security Updates(ESU)プログラムを利用し、追加料金を支払って1年間の延長サポートを受ける方法だ。現在のところ、ESUの価格は1年あたり30ドルとされているが、これは長期的な解決策にはならない。
次に考えられるのが、Windows 11へアップグレードすることだ。しかし、ハードウェアの要件を満たしていないPCでは、この選択肢が現実的でないケースも多い。特に企業や学校など、大規模なPC環境を管理している場合、一斉アップグレードはコスト面でも負担が大きい。
そして最後の選択肢が、Windows 10をサポート終了後も使い続けることだ。しかし、この場合はセキュリティリスクが大きな問題となる。定期的なセキュリティパッチが提供されなくなるため、新たな脅威に対する防御策が必要になる。ウイルス対策ソフトやファイアウォールの強化、オフライン環境での使用など、追加の安全対策を講じる必要があるだろう。
マイクロソフトがWindows 10のサポート終了を延期する可能性は現時点では低いと見られるが、一部のユーザーグループからは延長を求める声が上がっている。特に環境面での懸念として、大量のPCが廃棄されることへの問題提起もなされている。今後、ユーザーがどのような選択をするのか、Windows 10の最後の1年が重要な分岐点となる。
Windows 11への移行が進まない現状と今後の展望
マイクロソフトは積極的にWindows 11への移行を促しており、最近ではフルスクリーンのポップアップ広告を表示するなど、ユーザーに対してアップグレードを強く推奨する施策を展開している。しかし、多くのユーザーがこれに応じず、Windows 10のまま使い続けている現状がある。これは、OSの新機能よりも「現状維持の安心感」が勝っていることを示している。
Windows 11が持つ新機能やパフォーマンスの向上は確かに魅力的だが、一方で新しいタスクバーのカスタマイズ性の低下や、スタートメニューの変更といった点に不満を持つユーザーも多い。加えて、企業や教育機関での導入には時間がかかるため、組織全体の移行が遅れる要因となっている。
今後、Windows 11のシェアがどこまで拡大するかは不透明だが、Windows 10のサポート終了に向けて、ユーザーの選択肢が限られていくのは確かだ。仮にWindows 11の普及が進まなければ、マイクロソフトが再び方針を見直す可能性もある。例えば、Windows 10の延長サポートのさらなる拡大や、新たなアップグレード支援策の導入など、状況次第では柔軟な対応が求められるかもしれない。
Windows 10の時代が終わりに近づく中、ユーザーはそれぞれの環境やニーズに応じた最適な選択を迫られている。今後1年の間に、マイクロソフトがどのような施策を打ち出し、ユーザーの移行をどこまで促進できるかが、大きな焦点となるだろう。
Source:Windows Central
